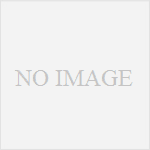第三章 異国の旅人達②
ひとつ大きな問題があった。クアラルンプールを出発し、マレーシア北部のペナン島にある世界遺産の町ジョージ・タウンに滞在している僕は頭を悩ませていた。タイで起こったクーデターについて、である。つい先日タイの軍が政府に対しクーデターを起こし、その影響でタイ国全土で厳戒令がしかれ、夜間は外出禁止という事態になっているのだ。マレーシアの北部から陸路で国境を越えてタイへと渡り、そのままさらに北上してバンコクを目指し東南アジアを周遊するというプランを考えていたが、実行できるかどうか不安が募る。
当然そのような突発的な事態に関してはネットで調べても対策が出てくるわけもなく、そもそも現状すらよくわからない。ペナン島のバスチケット売り場でも、ペナン島からバスで国境の町まで行き出国することはできるがタイに入国できるかどうかはお隣のことなので知らないとのことだった。おそらく情勢が刻一刻と変わっているのだろう。万が一入国できなかった場合、早速計画がストップしてしまう。飛行機に乗るようなお金はないため何が何でも陸路で行くしか無いのだ。その1ヶ国目の出口で足止めを食らうなどあってはならないことなのである。
朝、一か八かで国境へ向かうことに決めて宿を出た。バスターミナルへ行くとバスの出発は午後3時だという。待てど暮らせどバスは来なかったが、ようやく1時間半遅れでバスが来た。ダメならその時考えようと腹をくくって乗り込む。国境までは3時間ほどかかるらしく、到着する頃にはもう日が暮れているかもしれない。いろいろと不測の事態を覚悟していたが、実際はなんのことはなくすんなりと入国できてしまい拍子抜けをした。ただ、夜間外出禁止令がしかれていることにはかわりはないはずなのだが、大丈夫だろうか。出発時間が遅かったため着時間も夜9時頃になる見込みだ。心配したところでバスに乗せられてただ運ばれている身である、何もできることはない…。
国境近くの町、ハジャイへと辿り着いたのは案の定9時過ぎのことだった。夜間外出禁止令が出ているはずなのだが、街は普段通りであろうにぎわいを見せている。大きなショッピングセンターの前では人が忙しなく行き交い、おしゃれをした若者が集まって会話をしている。道は外灯に加えてどこからともなくやってきた屋台が、道端でキラキラと輝いている。ライトに照らされオレンジ色に輝く様々な部位のフライドチキンが並ぶ店、カラフルな魚の練り物の串の店、カットされた南国のフルーツ店などが並び、人々はそれらを買って食べ歩いている。見るからに平和そのものである。聞いていた話と違うと思った点がもう一つあった。タイ南部はイスラム過激派組織によるテロが頻繁に起こる超危険地帯だと聞いていたのだが、そんな雰囲気もかけらもない。
外国人旅行者にとっては平和であることは嬉しいことなのだが、なんだか肩透かしを食らい気が抜けてしまった。まずは今晩の寝床を探す事にし、事前にネットで名前だけ控えておいた宿へと向かった。乗合タクシーに乗り、宿の近くで降ろしてもらう。時刻はちょうど10時になろうとしていた。当たり前だが国境を越えると違う国になる。マレーシアの英語をローマ字読みに変換したようなマレー語の見慣れた文字の看板から、全く文字から意味が想像できないタイ語に変わっている。タイは1度一人旅で来たことがあるためそこまで不安はないのと、いたる所に英語表記があるためお目当ての宿を探すのはそんなに難しくはなさそうだ。
宿を見つけて中へ入ると、がらんと薄暗く広いロビーがあり、数人が座っているのが見える。その一角が受付のようだった。
「今日の宿は空いてますか?」
「空いてるよ、140バーツ」
一泊の料金はわずかに140バーツだと言う。タイの通貨はとても計算しやすい。ちょうど3倍にすればいいのだ。そんな安い値段でシングルルームに泊まれるのだから旅人にとってはこんなに素晴らしいことはない。それに厳戒令の有無はともかく遅い時間に知らない街で宿を探しまわらなくて済んだことに、ホッとしたのだった。
翌朝宿のおばさんに髪が切れそうな場所があるかどうか聞いてみることにした。クアラルンプールの宿で「髪を切る旅をしていて…どこかいい場所知りませんか?」と聞いた所その宿のおばさんの息子を切ってくれという話になった。屋上で高校生の息子をカットし、お礼にバックパッカーがありつけるはずもない豪華な食事をご馳走していただいたのだ。旅の中でどのように髪を切るかは未だ課題であった。誰も知る人がいない街というだけでなく、右も左もわからないのだから当然のことである。ひとまず同じ要領でおばさんに声をかけてみることにした。もしかしたら美味しいタイ料理にありつけるかもしれないと悪知恵も少し働かせたのだ。
「すいません、僕旅しながら髪の毛を切っているんですが、どこかいい場所知りませんか?」
「ヘアカットしたいの?それならここに行ってごらん」
地図を広げて丁寧に教えてくれる。宿のすぐ近くにそれほど最適な場所があるのだろうか?見た所、何らかの建物がある場所のようだ。外へ出て行ってみると遠くから赤、青、白のサインポールが見えた。まさか、と思って建物の前まで行ってみるとそこは床屋であった。宿のおばさんは僕が自分の散髪をしたいと訴えていたと勘違いしたようだ。いや、勘違いというより当然のことだと思った。わざわざ異国へ行って誰かの髪を切りたいなどという人間がいるとは普通は考えないからである。宿へと戻り再度説明をするとようやく理解してくれたようだった。
「それなら私の髪を切ってよ」
ニコっと笑って受付のおばさんはそう言ってくれた。なんとそんな事があるのか、と思った。客とは言え突如現れたどこの誰かもよくわからない自称美容師にそんなに簡単に自分の髪を任せるものなのだろうか。日本人的感覚なのかもしれないが、ごく一般的な感情で言えば「では、よろしく」と頼む日本人はほとんどいないと思われる。自分で髪を切りたいと言っておきながらなにを躊躇しているのだと思いはしたが、なんとも不思議な感覚であった。
思えばクアラルンプールの宿では「息子を切ってくれ」だから違和感がなかったのかもしれない。日本でもマレーシアでも母は息子の髪というものに対しては非常にザックリとしているのだな、とその時思った。伸びてモサモサするからカット代がかかって仕方がない、なるべく丸坊主に近い髪型にしてくれ、と美容師時代に息子を連れてきた母から注文されたことが何度かあった。その度に「お母さん、短くすればするほど伸びるのはすぐ気になるのですよ」と諭すように言ってみたりもしたが、たいていは「まあとにかくやっちゃって」といった雑な雰囲気であった。クアラルンプールの宿でもそれはヒシヒシと感じたのだ。
客がいない部屋に通される。東南アジア特有のプラスチックで背もたれがない真っ赤な椅子をどこからともなく持ってきて、あとは何が必要かと聞いてくる。とりあえずはほうきがあれば、と答えて椅子に座ってもらいカットクロスを巻いた。この旅では美容室にはかならずある鏡がない。プロの美容師は鏡越しにバランスを見たりするが、それが出来ないのだ。かと言って全く切れないわけではない。英語でカウンセリングをし、毛先を少し整えてすいてほしいとのことだった。
腰にシザーケースのベルトをまわす。日本で美容師になりたての頃原宿で買った黒の革で作られたシザーケースに、使い慣れた道具を入れて日本から持ってきたのだ。これはある種の儀式のようなもので、この相棒のシザーケースを腰につけると仕事というわけではないが、よしやるぞという気分になる。使い慣れた、黒く目が粗いクシでおばさんの髪を梳かしていると、宿にいた数名のおばさん達が掃除用具など片手に集まってきた。仕事もそこそこにカットしている様子を見物している。
フィリピンの語学学校にいた時は生徒の髪を切っている様子をフィリピン人の先生方がキャッキャとはしゃぎながら見物していたが、タイでもあまりそれは変わらないらしかった。なにを言っているかはわからないが、おばさん達が明らかにはしゃいでいる。僕に対してと言うよりは、髪を切られているその受付のおばさんに対してという雰囲気も感じられるが、茶化しているわけでもなさそうだった。
そうしているうちに髪を切り終わった。1人切れた事がそもそも奇跡的なことだと思っていた僕は、さて今日も仕事を終えたぞ、と最安値のビールを売ってる商店でも探しに行こうかと考えていた。ところがまわりではしゃいでいたおばさんが自分も切ってほしいと言い出したのだ。見ず知らずの外国人にいきなり髪を任せる人などそうそういないだろうと思っていたが、いた、それも2人もである。もちろん断るわけもなく、またプラスチックの椅子に座ってもらい、髪を切り始めた。
最後に切ったのは耳の上辺りまで刈り上げており、頭頂部だけ長く伸ばしている、例えるならばパイナップルのような髪型をしたおばさんだった。一通り整えて切り終え、落ちた髪をほうきで掃こうとすると僕の手からほうきを奪い取り、かわりに50バーツを握らせてくれた。日本円にして150円である。50バーツがあれば屋台で夕飯を食べるか、コンビニで大瓶のビールが買える。旅に出る前からすでに資金が枯渇している僕にとっては、とてもありがたいものだった。さすがに大金というわけではないにしても、これで1食が繋げた。明日も生きることができる。
日本では当たり前に髪を切ってお金を頂いていた。旅に出てからお金を請求したことはなかったし、鏡もない、シャンプーもない、ドライヤーもない状況でお金がもらえるわけがないとさえ思っていた。しかしおばさんはおばさんなりの感謝の気持として50バーツを僕に渡してくれたのだ。お金のために旅をしているわけでは決して無いが、素直に嬉しかった。おばさんに何度もお礼をいい、50バーツを握りしめきらびやかな夜のハジャイの街へと出かけることにした。