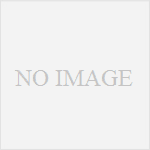第二章 旅烏の葛藤①
午後4時、韓国・ソウルの仁川国際空港に到着した。韓国へ降り立ったのは人生で3度目である。以前来た時は明洞でサムギョプサルを食べたり、東大門市場へ行ったりとずいぶんベタな旅をしたものだが、今回は特に観光をするつもりはない。東京のシェアハウスで一緒に住んでいた韓国人の友達に会うのが1番の目的だった。
入国審査の列に並ぶと、日本人がたくさんいることに気がついた。ここは外国なのだけど、感覚的にどこかまだ日本に片足を突っ込んでいるような気がしてくる。無事に入国審査を終え、レーンの上をグルグルと流れる手荷物を探す。この世界一周1000人カットの旅ではハサミを持ち歩くため、追加料金を払って必ず飛行機には預けなければならないのだ。ロストバゲージと言って、なぜか預けたはずの荷物が消えるという摩訶不思議な現象があるらしいということは事前に調べていて知っていた。ハサミが失くなったらその時点でこの旅は強制的に終わりである。1ヶ国目でいきなりそんなことにならないだろうかと妙にドキドキしながら待っていると、無事に赤いバックパックが流れてきてくれた。
バックパックを背負い、今度は税関職員が待ち構えるゲートへと向かう。“Nothing to declare“と書かれたゲートを「声をかけられないだろうか」とハラハラしながら通り過ぎる。規定を超えたタバコや酒など引っ掛かりそうなものは特に何も持っていないのだから呼び止められても問題はないのだが、ハサミが入っていることについてなにか言われたらどうしようかという不安はあった。海外では就労をする場合は当然ビザが必要になるわけだが、どう見ても美容師の仕事道具であるハサミを持っていて「観光で来ました。」と言うのも無理があるような気がしてくる。幸い声をかけられずに通り過ぎることが出来た。これから幾度となくこのロストバゲージの恐怖と入国審査と税関で変な疑いをかけられないかどうかハラハラしなければならないと思うと少し憂鬱である。
「おーい、バボちゃん」
【ようこそ、バボ様】と書かれた手作りの看板を持ってニヤニヤしながらそう叫ぶ男は、韓国人の元シェアメイトであるキューちゃんである。彼にはカン・ホンギュという名前があるが、発音が難しいということでそういったニックネームになっている。25歳の同い歳だ。約半年間にわたり同じシェアハウスで住んでいたのだが、引っ越してしまったあとも、昼過ぎから上野の安い居酒屋にホッピーを飲みに行くような仲だった。今はもうワーキングホリデービザの期限が切れたため、地元であるソウルに住んでイタリアンレストランで仕事をしている。
【バボ】とは韓国語でバカとかアホとかいった意味である。よくない言葉ではあるのだろうが、どちらかと言えば関西人の「アホ!なんでやねん!」のアホに近いニュアンスである。彼は僕のことをバボちゃんと呼ぶ。彼の他にも何人かの韓国人がシェアハウスにはいたが、そのみんなが同じように僕のことをそう呼んでいた。僕が酔っ払ってアホなことを言ったりしていたかららしいが、それはそれで気に入ってはいた。そして僕もまたお返しのように「バボちゃん」と彼のことを呼ぶこともあった。
「1時間くらいだからバスで行こう」
空港の外に出て、キューちゃんに言われるがまま大型のバスに乗り込んだ。しかし初めて韓国に来た時は外に出るとキムチの匂いがするような気がしたのだが、今回はそんなことはなく、特に何も感じない。
「キューちゃん、外国人が日本に来ると醤油の匂いがするってホント?」
「なに言ってるの。そんなわけないじゃん、バボ」
よく考えたらそれもそうだな、と思った。いくらなんでも大気中に醤油の成分が含まれるほど醤油は使ってないだろう。醤油工場の近くならまだしも、空港の周りなんてそもそも何も無いのだ。感じるとしたらある種の先入観と言うか偏見とでも言うのか、そういった類のものなのだ。インドに行ったらきっと「カレーの匂いがする」などと言うのだろう。しかし、なんとなくインドの場合は本当にカレーの匂いがしそうである。
「ジュンが来るから休みとったからね。明後日俺のおばあちゃんちに行こうよ。」
彼は日本語が妙に流暢なのだが、日本のドラマを見て独学で勉強をしたらしい。そのせいかどこか外国人が話す日本語にある堅苦しさのようなものがなく、非常に日本の若者っぽい日本語なのだ。ドラマの影響なのか元々の性格なのか、若干口も悪い。そんな彼は今回の僕の滞在に合わせて休みも取ってくれたらしく、滞在中のプランも考えてくれたようだった。空港での出迎えだって都内から成田空港へわざわざ迎えに行くようなものである。口は悪いが実は優しいところもある。
その日はキューちゃんオススメの食堂でご飯を食べ、実家に泊めてもらった。翌日は国際展示場のようなところで世界の酒の試飲会があり、同行させてくれた。おそらく飲食店や仕入れ業者向けの専門的な展示会なのだが、どういうわけか僕も飲食店の一員ということにして入れてくれたようだった。韓国語が理解できず詳細はわからなかったが、働いてるレストラン用のワインを探しに来たようで、試飲しながらメーカーと商談しているようだった。僕はその横で、なに食わぬ顔をしていろんなお酒を試飲させてもらい、ほろ酔いでいい気分だった。
世界一周を開始してからあっという間に2日が過ぎたが、今のところただ美味しいものを食べて飲んで遊んでいるだけである。全く髪を切れそうな気配がない。一体どこでどうやって髪を切る人を探したら良いのだろうか。そもそもヘアカットの旅の計画そのものがあまりにもザックリしていて、ほとんど決まってないようなものだった。行き当たりばったりでなんとかしようくらいにしか思っていなかったが、なんだか行き当たりもばったりもしてない。チラシでも作ればいいのだろうか、とそんな事を早速考え始めていた。
「キューちゃん、これから出会った人の髪切るためにどうしたら良いと思う?」
「あーわからないけど、明日おばあちゃんの家行くから髪切るか聞いてみよう。」
翌朝は早い時間に起き、地下鉄の1番線に乗ってソウル北部の街を目指した。ソウルは地下鉄が街を網羅していて移動には困らない。乗るためには四角くて大きい鉄の塊と言ったような機械で交通カードを買う。1350ウォン、日本円で約135円ほどでかなり遠くまで行くことができるため、日本の地下鉄より少し安い。電車とバスを乗り継いで1時間半ほどの所におばあちゃんの家があるという。ソウル以外の街に行くのは初めてである。とても楽しみだ。
1回電車を乗り換え、そのあと到着した駅前からローカルバスに乗り換えた。街の景色は大都会ソウルとうってかわってまさに田舎のそれである。韓国の田舎の風景は日本と違い、なんだか薄茶色く見える。まだ作物を植える前の田畑の土色に合わせたかのように、家も茶色い。山も遠くに見えるからか、全体的に緑が少ない印象だ。その中で時々飲食店の派手なデザインの看板が現れるのだが、飲食店のセンスは都会も田舎も同じらしかった。
しばらくそんな事を考えながらバスにゆられていると「もうすぐ着くよ」とキューちゃんが言った。そして降り立ったのは、近隣に特に建物も何も無いような場所だった。田舎というかもはや寂れた村のような所に来てしまったなと思ったが、そこは楊州市という街で、一応村ではないらしい。
「ついたよ。ここ。」
見るからに古い家がそこにはあった。日本人でも今や古い日本家屋に住んでいる人は少ないと思うが、田舎に行けば無いことはない。韓国でもソウルではこのような家は見たことがないが、近代化したとは言えやはり残っているところには残っているのだろう。キューちゃんが外から叫ぶと中から強めのパーマをかけた背の小さなおばあちゃんが出てきた。
「どうぞ、入って。」
キューちゃんの後に続き家の中に入ると、玄関を入ってすぐ広い居間のような部屋があり、そこにテーブルが置いてある。その上にはキムチ、ナムルが数種類、それからご飯、焼き魚、そしてスープとテーブルを埋め尽くさんばかりの数々の料理が並べてあり、とてもいい香りが漂っている。
「これおばあちゃんが作ってくれた。たくさん食べてだって。」
「え、こんなに?いいの?ありがとう。いただきます!」
キューちゃんに翻訳を頼み、日本から来たこと、美容師をやっていることなど簡単な自己紹介をしてから料理を頂くことにした。テンジャンチゲと呼ばれるスープは、日本で言うところの具沢山の味噌汁のようだった。チゲと言うが鍋でもなく辛くもなく、大根などの具材も柔らかくてとても美味しい。キムチや漬物もおばあちゃんが家で漬けているものだという。韓国の伝統的な家庭料理だそうだ。
外国人が日本に遊びに来たら寿司や天ぷらを食べるように、日本人が韓国に行けば甘辛い餅のトッポギや、鳥を丸々煮た薬膳スープのサムゲタン、豚バラ肉を野菜に包んで食べるサムギョプサルなど定番韓国料理を当然食べる。日本人が毎日寿司や天ぷらを食べるわけではなく、意外と家庭では質素に漬物や納豆などを食べるように、韓国でもそれは同じなのである。しかし、ただの旅行者がその国の家庭料理を食べる機会にはなかなか巡り会えない。こういうおもてなしが旅人の僕には一番ありがたかった。
食べながら疑問に思ったのだが、そう言えば韓国や中国では料理を残すのがマナーと聞いたことがあった。なんでも、食べきれないほど料理を出すというのがおもてなしとされていて、全部食べてしまうのは「物足りない」という意思表示になり失礼だとかそのような話だったと思う。キューちゃんに確認しても良かったのだが、僕は食べ物を残す事は失礼だとやはり思うから、気にもせずあれもこれもとテーブルの上にあるものは綺麗に食べた。何よりそうしたくなるほど美味しかったのだ。
食後には家の近所を少し案内してくれた。野菜を作っている畑、農作業の道具をしまっている倉庫、納屋など。おばあちゃんは畑仕事も自分でしているという。一通り見終わるとおばあちゃんにお礼を言って、記念に写真撮影をして家を後にした。
「おばあちゃん喜んでたよ。あんなにたくさん食べてくれて嬉しかったって。あと日本人初めて見たって言ってたよ。」
帰りのバスの中でキューちゃんはそう言った。やはりちゃんと食べて良かったな、と思った。確かに残す文化も国によってはあるのかもしれないが、作ってくれた人に感謝して残さないことは日本の文化である。郷に入っては郷に従えという言葉があるが、そのぐらいの流儀は通してもいいだろうと思えた。
それよりも驚いたのが「日本人を見たことがなかった」という言葉だった。太平洋戦争中の日本と韓国の関係性を考えると、てっきりすべての韓国人は日本人から何らかの直接的な影響を受けているものだと思っていた。韓国国内で反日の活動があるとのニュースを見たこともあるし、韓国人の年配の世代はあまり日本のことをよく思ってないのではないか、とも思っていた。中にはそういう人もいるのだろうが、おばあちゃんのように見ず知らずの僕のような日本人を快くもてなしてくれる人もいる。
東京のシェアハウスでも何人もの韓国人と仲良くなったし、韓国に来てからもキューちゃんの紹介で何人か一緒に飲みに行ったりもした。その人たちもみんな優しかったし、とても良い人だった。日韓の仲が悪いというニュースもよく見かけるが、これこそ百聞は一見に如かず、である。実際に来てみて感じることやわかることが、お隣韓国でさえこれだけたくさんあるのだと実感した1日だった。おばあちゃんの髪を切るのは美味しい料理を前にして、すっかり忘れていた。