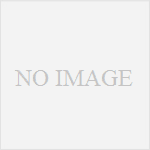第三章 異国の旅人達①
祖父の葬儀が終わり、東南アジアの何処かへと飛ぶことにした。当初はシンガポールに行く予定だったが、山梨から近い成田国際空港から飛行機を探した所かなり高額だった。そこで愛知の中部国際空港からクアラルンプール国際空港へと行き、その後シンガポールへと向かうルートはどうかと考えたのだ。その予想が当たり、安いチケットを見つけることが出来た。山梨から名古屋まで夜行バスで安く移動し、ようやくクアラルンプールにたどり着いたのはつい先程のことだった。もうすでに夕刻である。急遽マレーシアに来たもののどこに行く予定があるわけでもなく、知人がいるわけでもない。ただクアラルンプールは一度だけ来たことがあった。
1年半前に会社の夏休みを使いシンガポールとマレーシアに来た。その時はマレーシア南部の華やかな街マラッカで出会った日本人の男女3人組と仲良くなり、一緒にクアラルンプールに移動し観光をしたのだ。その時に行ったのがペトロナスツインタワー、それからチャイナタウン。当時は3人に任せてついて行ったものだから、どこをどう行ったらチャイナタウンに行けるのかサッパリわからない。だが、一度行ったことがあるというのはとりあえずすがりつくだけの価値がある。空港からバスと電車を乗り継ぎ、チャイナタウンまではなんとか辿り着くことができた。
まずは宿探しである。何ひとつとして情報もなければ相場もわからない。とりあえず駅を降りて歩いてみると、以前来た時には気が付かなかった賑やかさがそこにはあった。町に漂う香辛料の香り、路上の物売りに負けじと食堂のおばさんが必死に呼び込みをしている。フィリピンとはまた違う種類の熱気を感じ、知らない町に来たぞという高揚感があふれてくる。カレーのような食べ物、野菜と肉を炒めたものなどが10種ほど銀色のトレーに入れられて並んでいる。ライスといくつかのおかずを頼むシステムのようだ。食べたい気持ちを抑え宿探しを優先する。
以前チャイナタウンに来たと言っても、ただ夜にその辺のレストランでご飯を食べたというだけだ。その辺がどの辺かもわからないのである。町の中心部と思われるストリートに着き、さてどうするかと周りを見渡すと【BACKPACKERS BUDGET TRAVELLERS】という文字に目が止まった。どうもバックパッカー向けの安宿のようだ。歩き回るのも面倒だし、まずはそこに行ってみることにした。
「ハロー、今日の空きはありますか?」
カウンターに座っていたおばちゃんがニコッと微笑んだ。
「イエス、ドミトリーでいいかしら」
ドミトリーとはベッドがいくつか並んだ共同部屋のことを言う。だいたい二段ベッドが4つとか6つとか並んでいて、安く泊まろうと思えばそういう宿を選択することになる。
「一泊いくらですか?」
「15リンギット」
まだマレーシアの通貨に慣れていないため計算に少し戸惑ったが、一泊約450円ということだった。マレーシアの通貨はリンギットといい、1リンギットがおよそ30円である。1発目で当たりを引いてしまったようだ。他にも安い宿はあるかもしれないが、日も暮れてお腹も空いていたため即決した。
荷物を置き早速町中へ出た。もう完全に日が暮れようとしていて、町に明かりが灯りはじめている。外へ出て見上げると、まさしくチャイナっぽい赤い提灯が頭上を彩り、華やかな雰囲気と、町を行き交う人々の喧騒は想像していた東南アジアの熱気そのものだった。先程呼び込みをしていた食堂へと向かう。どうしてもそこにあったカレーのような食べ物が気になったからだ。よく見ると銀色のトレーには3種類のカレーがあるようだった。
「すいません、このカレーは何が違うの?」
「それはカレーじゃないよ」
「じゃあこれは何?」
「それはマレー料理だよ、カレーとは違う」
店のおばさんはこれはカレーではないのだと言い張る。あまり辛くはないらしい。良いから食べてみろといった感じでめんどくさそうにしているため、適当に1つ選び、ライスを一緒に頼んでテーブルで待っていた。運ばれてきたそれをマレーシア語でなんと呼ぶのかわからないが、見た目はカレーそのものである。食べてみたところ、やはりカレーである。テレビでカリフォルニアロールと呼ばれる巻き寿司が特集されていた時に「これは寿司じゃないだろう」と思ったが、何が違うかはうまく説明できる気がしない。おばちゃんもそんな気分なのかもしれないが、とにかく違いはわからない。
マレーシアは面白い国だ。白くててっぺんが平らな特徴的な帽子を被った浅黒くヒゲが濃ゆいイスラム圏にいそうな男性、過去にインド人に会ったことはないのにどう見てもインド人の男性、肌が白く見た目は中国人にそっくりな人、などいろんな民族と文化が混合している。チャイナタウンのようにインド人街やイスラム人街もあるのだろう。カレーをスプーンで食べつつ、明日はどこへ行こうかなんて考えていると、目の前に座ったおじさんがおもむろに右手でカレーとライスを食べ始めるのが見えた。親指と人差指と中指で器用にライスをつまみ、口に運ぶ。インドでは右手でご飯を食べると聞いたことがあるが、マレーシアにいるこの男性はインド人なのだろうか。マレーシアの食堂にいるのだからマレーシア人なのだろうが、国をこえて伝わる風習や文化とは面白いものだな、と思った。
宿にはイギリスから来た兄弟、ドイツから来た女子大生の2人組が泊まっていた。洗濯物を干そうと屋上の広場に行くと彼らがいた。「はじめまして。日本人のジュンです」と挨拶をし、今日から世界一周の旅に出るのだと聞かれてもないのに宣言した。1ヶ月以上前にこの旅が始まったとはいえ、実質的に語学学校にいて旅はしていない。本当の意味で今日がその始まりである。日本を出てまだ24時間も経っていないから当然といえば当然だが、高揚感はまだ薄れていなかったらしい。積極的に話しかけてみたくなった。彼らはとても歳が近かった。ドイツ人の女子大生ビビとアナは23歳。みんな長期間東南アジアを旅している先輩である。
「私達もうこれから帰国するの。東南アジアは本当に良いところだった。帰るのがさみしい」
「本当?明日そのままドイツに帰るの?」
「明後日ね。でもあっという間だわ」
「それはさみしいね。東南アジアで良かったところはどこ?」
「タイの小さな島は本当に楽しかった。お酒とパーティと…」
「そっか、この後タイに行くから行ってみたいな」
「絶対に行って!私達はもう行けないかもしれない…」
「どうして?」
「ドイツに帰ったら就職しなきゃならないの。学校の先生になるから。そうしたらタイにはあまり行けないかなって」
「そっか…」
行ったこともなければ見たこともない光景を話す彼女たちはとても楽しそうだった。母国から遠く離れたアジアの地で、今しかないと思いながらいろんな出会いや発見をポジティブに受け止め、楽しんだのだろう。彼女たちを見ていると、これから僕もこうなるのだろう、いや、こうなりたいと思った。ビビとアナはドイツの南部コブレンツという街の出身だという。世界一周の道中、ヨーロッパに来ることがあれば立ち寄ってほしいと言ってくれた。
「やあ、どこから来たんだ?」
「僕は日本から、君は?」
「俺はアダム、チュニジアから」
「遠いところから来たんだね。僕はジュン、よろしく」
「よろしく」
泊まっている安宿でそう話す彼は名をアダムと言うらしい。チュニジアなんて聞いたことこそあるものの場所が定かではない。なんとなく、ヨーロッパのほうだろうと思い「遠いところからわざわざ」なんて言ってみた。大体マレーシアにいるマレーシアっぽくない人はわざわざどこかから来ているのだし、僕だってその1人だ。
アダムは20歳で4ヶ国語を話す秀才らしかった。濃い眉毛と凛々しくくっきりとした顔立ちからはあどけなさを一切感じることは出来ず、30歳くらいに思ったがそれは黙っておいた。マレーシアで何をしているのかよくわからなかったが、つまり旅をしているらしい。
「僕は世界を旅をしながらいろんな人の髪を切ってるんだよ」
「それはいいね。じゃあ切ってくれる?君に任せるから良いから似合う髪型で頼むよ」
「いいの?よし、じゃあ切ろう」
フィリピンでは学校という環境ありきでヘアカットをしていたわけだが、それ故に本来の目的である【旅をしながらヘアカット】が出来たわけではないと思っていた。語学学校に通おうが旅は旅なのだろうが、どこか自分の中でイメージしていた形とは違っていたのだ。そういった意味ではアダムの髪を切るのは紛れもなく”旅の中で”と言えるだろうし、実質この旅初のヘアカットだ。宿の屋上へ行き、いつものようにカットクロスをつけヘアカットを行う。フィリピンで野外ヘアカットについては繰り返し行っていたため、その点はすでにかなり慣れたように思う。少し整えるように全体をカットしていく。襟足やもみあげの部分は丁寧にハサミで刈り上げ、頭頂部も整えた。
「ジュン、気に入った。ありがとう」
「それは良かったよ。ありがとう」
プロの目から見るとほとんど長さも形も変わっていないのだが、気に入ってくれたようだ。どこか外国人特有のお世辞のようなものを感じなくもなかったが、悪い気はしなかった。それにアダムとの出会いはとてもヒントになった。宿で会う旅人の中には長期旅行者も当然いる。髪の毛を異国の地で切ることに不安を感じるのはどこの国の人でもあまり変わらないらしい。どうせ切るなら、と選んでもらえるならこの1000人ヘアカットの旅も順調に進んでいくことだろう。