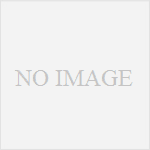第一章 生きてる実感⑤
「これさっさと運んで!三階ね!」
階段で三階まで重たい荷物を運ぶのはかなり大変だった。日当6500円、交通費は無し。その日の現場は二俣新町駅という聞いたこともない駅で、住んでいる下北沢からは1時間以上かかる場所だった。出会った人と握手をしながら日本を縦断するという旅を終えて無一文で東京に戻った僕は、日雇いの派遣の仕事で食いつないでいた。重労働の引っ越しの仕事は本当に過酷だった。
元々働いていた会社の先輩の紹介で、東京の飯田橋に新たにオープンするという美容室で就職が決まったのもその頃だった。4月頃のオープンに向けて準備中ということで、それまでは派遣の仕事をすることにしたのだ。旅に出たものの、美容師を諦めるつもりは毛頭なかった。また東京で再起を図ろうとアパートも借りたままにしておいたため、家賃で貯金が消えてしまった。もし引き払っていたらもっと長く旅をしていたと思うが、どちらかと言えばその後の生活を優先したのだ。
日雇いの仕事は日々現場が変わる。東へいけと言われれば行くし、西へいけと言われれば行く。荷物を運べと言われれば運ぶし、検品しろと言われればする。楽しいと思うことは一度もなかった。現場が一緒になった30代の人に「これで普通に生活出来てるんですか?」と聞いたことがある。その人は無理だ、と言った。親と一緒に生活し、ギリギリだという。働かなければ生きていけない、安くて嫌な仕事でもやらなければならない、長時間労働で安月給の美容師のほうがまだ好きなことやれてるだけましだなと感じた。
そんな生活をしてなんとか生き延びていたある日、日本中のあらゆる人の人生を一瞬にして変えてしまった出来事が起きた。東北地方太平洋沖地震だ。2011年3月11日14時46分18.1秒、マグニチュード 9.0、最大震度7。日本での観測史上最大の超巨大地震である。
ニュースでは各地を津波が襲う様子が流され、仙台市若林区では200人もの遺体が見つかったとの情報が流れ、陸前高田は壊滅、真っ暗な中燃え上がる気仙沼の映像に愕然とし、言葉を失った。日に日に跳ね上がっていく死者数、爆発する原子力発電。日本は終わりなのかと本当に思ったのだった。
「仙台で会ったあの人は?」
「旅を教えてくれたジョージさんは?」
震災発生のほんの1.2ヶ月前に僕は東北のその地にいたのだ。仙台駅前では何百人もの人と出会って握手をした。
「握手をしてくれたあのお兄さんは?」
「福島から来たと言っていたあのおばちゃんは?」
「黒板消しを買ってくれた女子高生は?」
mixiを交換した人もいるが更新はない、名前も住所も知らないあの人やあの人がどこでどうしてるかなんてわかるはずもない。あの旅で僕に物を与えてくれた人、お金を恵んでくれた人、家に泊めてくれた人、車に乗せてくれた人、そんな【あの人】がもしかしたら津波で亡くなったのかもしれない…。考えたくはなかったが、考えずにはいられなかった。
僕はあの旅で様々なことに気付かされた。それは勝手に気がついたのではなく、出会った多くの人からの恩によってもたらされた産物であった。握手をすることを通して、人の優しさに【気づかせてもらった】のだ。強烈な不安と胸が締め付けられるような想いに苛まれ、居ても立ってもいられないといった気持ちになった。
就職する予定だった美容室は既存店舗の水道管などの故障により出店延期が決まり、実質的に再就職の話は消えた。派遣の仕事もパッタリとなくなってしまった。その日食べるのもギリギリで、月末には68000円の家賃を払わなければならない。家賃を払うために働いているようなもので貯金はゼロだった。
震災によって直接的な被害はないものの、職も口座残高もないという状態にはなってしまった。だが、絶望しているわけではなかった。それもまた、旅をしながら野宿をしたりした経験から「なんとかなるだろう」とは漠然と思っていたのだ。震災3日後に下北沢駅へ行くと、若者が募金をお願いしますと叫んでいた。何もしてない自分が急に情けなくなり、財布の中身の全財産をすべて募金した。53円だった。
それから1ヶ月半がむしゃらに働き、まずは家賃の支払い分の確保、そして交通費分を稼ぎ、1週間は休んでも支払いが滞らないような状態を作った。旅をともにしたバックパックにキャベツ一玉、食パン8枚切り、着替え、歯ブラシ、寝袋を詰めて東京駅から福島県いわき市へ行くバスに乗り込んだ。
仙台もしくは宮城に行くことも考えたが、テレビからしか情報を得られなかった僕は、宮城と岩手はたくさん報道がされていたため多くのボランティアがすでに集まってるのではないかと考えた。原発事故の風評被害も大きかった福島県は、それに比べて人が少ないのではないかと思い、あえていわき市へ行くことにしたのだ。
3時間半後にいわき駅に到着した。正直驚いた。街はまったく普通の状態に見えたからだ。土地勘もなければ何もわからないため当然といえば当然だが、駅のあたりは津波の被害がないということを知らなかった。というより津波の被害があるのは海に近い集落や港など全体から見たら一部のエリアでしかないようだった。
冷静に考えればわかることだったが、てっきり僕はご飯を買うところもないのだろうと思い、最低限なんとかなるようにと腐りづらいキャベツと安かった食パンを持参したのだった。
社会福祉協議会が行っているボランティア受け入れのところで記名をし、早速作業をすることになりおじさん達のグループに入った。見る限りでは僕が1番若い。向かった先は豊間と呼ばれる地区だった。すでに地震発生から2ヶ月近くが経ちある程度は片付けられている事はわかったが、それでも強烈な衝撃を受けた。半壊している家がかろうじて残る以外、ほとんどが基礎だけになってしまっていた。曲がったカーブミラー、潰れた車、鉄骨だけになった何か。崩れた防波堤にボロボロになったランドセルが置かれているのを見た瞬間に泣けてきてしまった。
「津波とはここまですごいのか…」
手を合わせてみると、一人のおじさんがランドセルの横に花束をそっと置いて同じように、手を合わせて目を閉じた。
「ひどいもんやなぁ…」
おじさんがボソッとつぶやく。本当に言葉もないとはこのことだと思った。酷いななどという感想しか出てこない。それほどに酷かった。
「キミはどこから来たんや?1人?」
「東京です。1人です。」
「そうか、偉いなぁ。ボクは奈良から来たんやけどな。あの津波の映像を見てから行かな行かな思ってたんやけどな、ようやく来れたんや。」
半壊した家から土砂を掻き出し敷地の一部に積むという作業をひたすら繰り返した。おじさん達が思わず声を漏らすくらい、キビキビと作業をした。土砂を掻き出し、ネコで運び、積む。掻き出し、運び、積む。何往復したかはわからないが、引っ越しの仕事よりは重労働だった。しかし僕が福島に滞在できる時間には限りがあるからと、とにかく最大限貢献しようと休まずに動き続けた。
作業が終わり、撤収するという頃に1人のおじさんが「集合写真を撮りませんか」と言った。作業をした半壊している家の前で、である。「それはないだろう」と思ったが、その場の空気に流されて何も言えずに一緒に写ってしまった。その夜は公園の水道で頭を洗い、食パンを食べて、駐車場に寝袋をしいて寝ることにした。疲れているはずなのに、昼間の悲惨な光景だけでなく撮影の後悔と葛藤があり、なかなか寝つけなかった。
翌日は薄磯地区に行った。イワシの加工工場の中の土砂やヘドロを掻き出すという作業だったが、その日は気温も高くなんらかが腐った匂いが常に立ち込めていて、目眩がした。朝食べたキャベツと食パンを吐きそうになりながらも、なんとか作業を続けた。旅で出会った東北の人たちに恩返しをしたい。たくさん助けてもらったから、少しでも手助けをしたい。ただただその一心で。
昼休みに休憩もせず周辺を歩き回ってみた。海岸沿いに続く道はことごとく壊れ、分断されていた。震災当日には忙しなく走り回り、住民に避難を呼びかけていたであろう消防車は後ろの半分が失くなっていた。小高い丘のような所に登ってみるとそこには神社があった。神社へと向かう階段には多くの写真とアルバムが置かれていた。きっと誰かが見つけて、持ち主のためにそこに置いたのだろう。持ち主がその事実をただただ知らないのか、もう見つけることが出来ないのか、僕にはわからなかったがとても胸が苦しくなった。
2日連続で野宿をすると流石に体中が痛くなった。まともに寝られるわけもなく、疲れが溜まっているのを感じた。ただキャベツをムシって食べ、味のないパンをそのまま食べるといった食事にも嫌になってきて、コンビニで小さいポテトサラダを買って挟んで食べたりもした。それだけでもだいぶマシになった。
3日目の作業中に一緒になったおじさんに「ホテルどこなの?」と聞かれ「実は公園で寝てます」というと、とても驚かれた。その一言で僕にはお金がないということ察したのだと思う。夜、駅前で営業しているホルモン焼き屋さんに誘ってくれた上に、車で寝ていいよ、と鍵を渡してくれたのだ。久しぶりに暖かいものを食べ、暖かい場所で寝ることが出来た。ボランティアに来たのにボランティアされているようで、なんだか申し訳なかった。
小名浜漁港へ行き作業をしていた日のことだった。その日は釣具店の中を片付けるという作業をボランティアの団体と一緒にした。僕1人とその団体といった感じで、よそ者感があったからなのか1人の男性が話しかけてくれた。彼から聞く所によると、佐賀県から約20名で24時間近くかけてやってきたという。特定のグループではなく、佐賀県の社会福祉協議会が募集して応募してきた人たちで、僕と違い東北に来たこともないという人が殆どらしい。それなのにそんな遠くからすごいな、と頭が下がる思いだった。
作業をしながらいろいろと話し込み、その夜そのグループの夕食会に誘ってもらえた。駅近くにある地元の居酒屋を予約していたらしく、10名ほどでその店に向かった。図らずともまた温かい食事にありつけた。その居酒屋の従業員の話では震災直後は放射線を気にして山梨県に子供を連れて避難したりしていたらしい。当時の様子などもポツポツと話してくれた。
ボランティアをしている中でこんな話も聞いた。麦わら帽子を被った地元のおじいさんに挨拶をすると「この辺一体はどの家も最低1人は家族を亡くしてる」「娘は一度逃げたのに携帯を取りに家に戻って流された」と言った。悲しい表情をするわけでもなく、悲しそうに語るでもなく、まるで畑の野菜がキジに食われてしまったとでも言うような、少し残念そうな様子であった。きっと僕に何かを伝えたかったのではなく、その事実を口にして少しずつ気持ちの整理をしているのだろう。そう思うことにした。