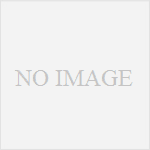第二章 旅烏の葛藤⑥
部屋のベランダから朝日が差し込む。日が昇ると遊びに来るキジトラ柄の野良猫がいた。窓をあけるとゴロゴロと喉を鳴らして寝転ぶ姿がとてもかわいらしく、たまには撫でたりしながら良好な関係を築けていた。語学学校の朝は毎日早い。朝ご飯を食べ、支度をしたらすぐに授業が始まる。気付けば自然と7時すぎには目が覚めるような体になっていて、その日もまた同じ時間に起き、ベランダにいるかもしれない猫に挨拶をすべくベッドから体を起こした。ふとスマホを見ると妹から大量のラインが来ているのに気がついた。ボンヤリと何かがあったなと思いはしたのだが、あえて確認はせずそのままベランダに向かう。猫はまだ来ていない。僕はあと数日後には学校での滞在を終えてシンガポールへ飛ぶことになっている。ここ最近は「猫と会えるのは今日が最後かな」と思うようになっていた。
少しがっかりしながら食堂へと向かい、いつものようにご飯とキムチとおかずをトレーに載せて食べ始めた。1ヶ月近くもいるからか、ほとんどの生徒とは話したことがあるような状態で、最初の頃感じていたアウェイ感のようなものは一切なく、以前東京で住んでいたシェアハウスと同じような、自分の家のような感覚になっていた。本当にあっという間の1ヶ月だった。思い返せば庭で髪を切り、桟橋で夜な夜なビールを飲み、クラブなどでフィリピン人と遊んでとなかなか濃い日々を過ごしたものだ。卒業して出ていくのが少しさみしいが.これから本当に僕の旅が始まるのだ。
朝食を済ませ、部屋に戻りスマホのメッセージを確認した。なぜか嫌な予感がしていたのだが、案の定、メッセージには実家で一緒に暮らしている祖父が亡くなったと書いてあった。旅に出る前から薄々とだが、こんな事もあるのではないかと考えていた。祖父は10年以上寝たきりで、離れて暮らしていたためあまり会うこともなく、話もほとんど出来なかった。出国前最後に会った時に「また1年くらいで帰ってくるから、元気でね」と言い、頷く姿を見てから家を出た。まさかその1ヶ月後に亡くなるなんてという信じ難い気持ちと、90歳だし仕方がないことなのだろうという気持ちと、シンガポール行きの飛行機のチケットを捨てて日本に帰る費用がさらにかかってしまうという貯金がないゆえの不安と、そして悲しい気持ちと複雑な感情になった。
母に電話をかけ、自宅で亡くなった時の様子を聞いた。人が亡くなる時どういう最後が良いのかはわからないが、やはりこれは仕方がないこと、寿命ということなのだろう。どうしても受け入れられないというわけではなく、変に冷静な自分に少し驚いたりもした。というより実感がわかなかっただけなのかもしれない。通夜と葬式の日程を聞くと、翌日のフライトであればどちらも間に合うらしい。学校のマネージャーに相談し、翌日のフライトを探してもらうとすぐに見つかった。直前のため値段は高いが、それに乗る事にし、授業などもキャンセルさせてもらう事になったが卒業前ということもあり実質的に1日だけキャンセルになるようだ。
急に帰るのに何も言わないのもおかしいと思い、学校の友達や先生にはその通りに話した。多くの人が大丈夫か、無理してないかと声をかけてくれた。日本ではそういう時ほどそっとしておくというか、あまり多くは語らないような気がするのだが、文化の違いだと思うが韓国人の友達は神妙な顔をしつつ特に気にして声をかけてくれた。その度になんだか申し訳なくなってしまい、大丈夫大丈夫と気丈に話すことで気が紛れたように思う。
ドドンの友達2人の髪を切る約束をしていたのを思い出した。初めて彼に会ってバスケをした後向かった学校の裏手にある、人が全く来ないような場所で髪を切るという話になっていたのだ。ドドン達にはあえて祖父が亡くなった話はしなかった。かわりに翌日の深夜便で帰らなければならないこと、会えるのは今日が最後だと思うということを伝えた。
最後の日も髪を切ったり、学校の授業を受けたりとごく普通の1日を過ごした。夜になり、学校に来た初日に行った近所のガーデン・バイ・ザ・ベイというバーで僕の送別会をやってくれるという。多くの人が翌日のテストのため勉強をしなければならない所、ほっぽりだして参加してくれたのだ。本当に嬉しかった。ガーデン・バイ・ザ・ベイは海辺にぽつんとあるからか、遠目にもキラキラと光り輝く姿が美しいお店だ。竹や木で作られた店内、テーブルや椅子も自然な感触で落ち着くし、壁さえないためすぐそこには海が見える。外から吹き込む風に当たりながら音楽が流れていてとても雰囲気が良い。
バーをでて学校を出発する前最後に写真を撮ろうということになり、みんなが集まってくれた中、ドドン達も来くれた。学校の生徒とは関わりがない彼らが生徒を見送るということは異例のことらしいが、僕はとても嬉しかった。やがて迎えのタクシーが来た。みんなが手を振る中で、手を振り返し、タクシーに乗り込む。事情が事情なのかもしれないが、こんな盛大なお見送りはこれまで見たことがなかったから、それも純粋に嬉しかったし有り難かった。またいつか会いたい、またここに来たい。また会いましょう、世界の何処かで。
これから長旅である。タクシーでダバオ空港まで行き、そこからマニラのニノイ・アキノ国際空港経由で成田国際空港へ。そこから新宿まで電車で向かい、新宿からは高速バスに乗る。急を要するため仕方がないが20時間以上の大移動をしなければならないのだ。飛行機では少しだけ寝れたが、乗り換えなどであまりゆっくりと寝る時間はなかった。旅に出てわずかに1ヶ月だが、今回の旅程が一番大変である。
ようやく家についた僕を見た親戚が「黒くなったなぁ。フィリピン人みたいだ。」と言ってきた。どう反応したらいいかわからず「まぁ」と言って家の中に入る。身内が亡くなった経験がなく、葬式仕様の家になっていて少し驚いた。田舎だからかわからないが、誰かが亡くなると通夜まで2.3日は家の布団に寝かせておき、近所の人や友人、親戚などが昼夜問わず挨拶と線香をあげに来る。両親はその対応に追われているようだった。
喪服の人があふれる中、半信半疑でフィリピンから帰ってきて、その疲労を表すかのようによれたTシャツとダバオで50ペソで買った汚れたジーンズ、ビーサンにバックパックというかなり場違いな姿の孫を見た人はどう思ったのだろう。先に着替えるわけにもいかず、布団で眠る祖父とそのままの姿で対面した。青白い顔、鼻に詰め物がされていて明らかにもう息をしていない事がわかる。聞かされるのと見るのは全く違うということは旅をしていて常々思うことであるが、まさに百聞は一見にしかず、ようやくそこで祖父の死を実感したのである。
実感とともに悲しさなのか寂しさなのか、いろんな感情が溢れ、それとともに涙も溢れてくる。身内の死というものはこうも大きいものなのかと思いつつも、最後に顔を見れたことは本当に良かったと思った。それを見ていた葬儀屋が「今までいろんな人の最後をみてきましたが、孫が泣いてくれるような人は、本当に良い人生を送れた幸せな人なんです。」とポツリと言った。
祖父はとにかく無口だった。酒好きで醉うと過去の一人旅について武勇伝のように語る人だった。おにぎり1個だけもって下駄で富士山頂上まで登った話、金を持たずに神社などで寝ながら伊豆半島一周してきた話、海の水がしょっぱいことを確かめるために海水を舐めに行った話、そんな話しを小さいときはよく聞かされてウンザリしていた。
戦後、未開の土地を本家からもらい、そこに小屋を建てて畑と織物業をやり始めた祖父と祖母は、それはそれは貧乏で朝から晩まで働き詰めだったという。四人の子を育て、父から祖父になり、ようやくゆっくりとした時間がとれるようになった頃に体を壊して寝たきりになってしまった。ついに軽トラに乗り日本一周するという夢を叶えることなく、亡くなってしまった。旅をするような家族は他に1人もいないのだが、どういうわけか僕も一人旅が好きなのだ。その血を引いているような気がしてならないのは僕だけではなく、祖母や親戚からも「おじいちゃんに似てる」なんて言われたりもした。
実際世界一周の旅に出ると言った時のまわりの反応は心配や不安といったものがほとんどであったが、祖母だけは「おじいちゃんと似てるから仕方がないな」というようなことを言ってたのを覚えている。長年連れ添い、祖母は祖父のことをそのように理解していたのだろう。僕自身も、今になってみれば祖父の気持ちはなんとなくわかる気がする。子供の時はうっとおしい自慢話のように思っていたが、今思えば僕も同じようなことに魅力を感じ、同じようなことをしているのだから。
みんなで旅行に行って高級な料理を食べ、良い旅館に泊まり、贅沢をすることに価値を感じることが出来ず、それよりももっと大事なものの為にどこかに足を運びたいと考えるその気持ちを。僕も祖父もお金がない中でただ単純にそういう事ができなかっただけということもあるが、それもまた運命だと思うのだ。お金がなくても目があれば景色は見ることが出来る、口があれば人と話せるし、足があればどこへだって行ける。お金に縛られず、自分の興味がわく場所や、やってみたいと感じること、見たいものを見ること、そのすべては自分の好奇心と経験のため。旅は遊びではなく、自分が自分らしく生きるためにするものなのだ。
人が死んだら、残された人達は悲しむだけ悲しんだ後に、その人に対して「天国から見守っててね」などと言ったりするが、僕はそうは思わなかった。死んで極楽というところに行くのであれば、祖父もこれであらゆる苦しみや葛藤、後悔から解放される。残された人達のことなど気にせず、一人気ままに旅にでてもらいたい。そういった想いを込め、棺桶に「旅」と書いた一円玉を入れた。
祖父はよく「一円玉の旅ガラス」という歌を何度も何度も聞かせてくれた。
”一円玉の旅がらす
ひとりぼっちで どこへゆく
一円玉の旅がらす
あすは湯の町 港町”
このような歌詞で、子供だった僕はこの歌にもウンザリしていたが、今となってはなぜ祖父がこの歌が好きだったのかわからなくもない。お金も持たずに旅に出るような祖父らしい歌であるとともに、自分自身もまた行き着く先がどこかわからない旅烏になったのだなとふと思ったのだ。一円玉は僕から祖父への最初で最後の贈り物であり、これからの旅が良い旅になりますようにと願を込めたお守りである。
旅に出たくても出れなかった、その葛藤を抱えつつ今まで苦労を重ねて生きてきた祖父の意志は、これから僕がついでいく。願わくばいつか旅の話を聞かせてほしい。そして僕もいつか面白い旅の話ができるよう、様々な葛藤を抱えながらも旅を続ける旅烏として生きていく。これからが本当の旅の始まりである。