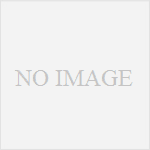第二章 旅烏の葛藤⑤
頭が茹で上がるような暑さのフィリピンにやってきて早くも2週間が経った。それでもまだこの暑さにはなれず、日に何度も暑い暑いと口にしてしまう。日差しが強く、直射日光の下を歩けばジリジリと肌が焼ける。せめてもの救いになればと葉っぱが生い茂る木の下で太陽を避けながらも2日か3日に1回は生徒や先生のヘアカットをしている。
髪を切った数はすでに15人を超えていた。そこまで切ってようやく気がついたことだが、日中に外で髪を切るのはなかなかキツイものがある。夜切ればいいかと言えば暗くて見えないし、室内ではどうしても毛が落ちてしまい掃除がやりきれない。日中、そして外で切るしかないのだ。桜舞う春のような気温と日差しの中で髪を切れたらきっとストレスはないのだろうが、常夏の島にはそんな穏やかな日は存在しない。どうやら僕はとんでもないことを始めてしまったらしい。これをあと950人以上繰り返すなどということは、狂気のように思えた。
庭で人の髪を切っていると、そこが目に付く場所でもあるからなのか、授業で顔を合わすことがなく関わりが全くない先生からも「ヘイ、今度髪の毛切ってよ。」などとニヤニヤしながら声をかけられるようになってきた。真剣なのかからかっているのかわからないが、先生たちはみんな20代から30代と若く、すごくノリが良かった。何がそんなに楽しいのか、いつも冗談を言い合ってケラケラと笑っている。
その先生方も授業ではとても熱心に教えてくれる。肝心の英語学習の方はどうと言えばそこそこ頑張ってはやれている。毎週末にある単語テストに向けてみんな夜遅くまで机に向かってカリカリとノートに単語を書いているが、僕は学校の裏手にある素敵な桟橋で月明かりの下ビールを飲みながら勉強するといった怠けっぷりである。みんなよりは頑張ってはいないが、ちゃんと勉強はしている。だから頑張っているということにしている。一度ノートに書いてみたこともあるが、どうしてもそれでは覚えられないし集中できないのだ。
学校の敷地の入口と反対側、つまり建物裏側にはフェンスがあった。そこをサッと乗り越えるとすぐに静かな浜とそれなりに月日が経っているであろう味のある桟橋がある。見たことはないが、桟橋からは船が出たりするのだろうか。夜そこに立てばもちろん暗いのだが、すぐ目の前に遅くまで明かりがついている学校があるからか、どこか落ち着ける暗さであった。
月明かりが反射してキラキラ輝く海の静かな波の音と一緒に好きな音楽を聞きながら、桟橋に寝転がる。両手でA4サイズの紙を広げて週末のテストに出る英単語の一覧とにらめっこを始める。そしてただただ、単語とその意味を声に出して復唱する。学校敷地内は禁酒だったが、桟橋なら誰も来ないしいいだろうと近所のスーパーで買ったビールを持ち込んで、飲み終わったら帰るといったオリジナルの方法で学習に取り組んでいた。そんなものでテストの点が取れるのかと学校で仲良くなった人には言われたが、だがそれが1番効率よくストレスもなく覚えることができ、テストの点も取れていたのだ。学生時代は勉強が苦手だったと思っていたが、やり方の問題だったようだ。
静かな夜の桟橋はいつしか僕の定番スポットになっていた。たまにテスト勉強をサボって、友達と一緒にビールを飲みながら語り合ったこともある。母国にそれぞれ彼氏と彼女を置いて1人で留学に来ているという韓国人同士の留学中限定不倫カップルが、みんなに隠れてこっそり現れたらこともあった。まさか灯りもない桟橋でビールを飲みながらテスト勉強している奴がいるなどとは夢にも思わない2人は、僕を見るなりギョッとした顔をして、気まずそうにすぐに目をそらした。あえて何も言わず、暗くて気が付いてないふりをしたが、なんだか楽しそうでいいな、と思った。
勉強以外の時間もそれなりに充実していた。フィリピンではジプニーと呼ばれる乗合バスがあちこちを走っている。ジプニーは運賃6ペソ、およそ12円で乗ることが出来る。車のボディ側面に行き先や経由地がざっくりと書いてあり、乗り換えたりすることでかなり遠くまで行くことが出来る人々の大切な足なのだ。トラックの荷台に屋根を張り付けたようなデザインで、窓はない。車の色は様々で鮮やかなブルーもあれば土埃で汚れた白い車もある。車の後部が開いていて、そこからそのまま乗り込むといったスタイルだ。
新たな乗客が乗ってくると、すでに座っている乗客は腰を浮かせてどんどんと奥に詰めていく。運賃の支払いは乗った時にドライバーに直接支払うのだが、新たに乗ってきた人は車の後部、つまりドライバーとは一番遠い所に座る。そのためバケツリレーの要領で新たな客がポケットから出したコインを隣の人にどんどんと渡して支払うという全面的に乗客の協力ありきのユニークな乗合バスなのである。降りる時はコインで手すりをカンカンと叩くと好きなところで停めてくれるため、慣れてしまえばとても便利である。
暇を持て余したとある週末、ジプニーに1時間ほど乗って街の郊外へ行ってみることにした。特に何か目的があるわけではないのだが、無性にどこかフィリピンらしいところに行ってみたくなったのだ。行き先不明のジプニーが目の前に停まり、中には数人がすでに乗っている。6ペソを隣に座ったおばさんに渡して、しばらく外を眺めていた。道端には様々なお店が並んでいて、何かがあるわけではないのだろうが人が多く賑わっているように見えた。気まぐれで手すりをカンカンと叩き、降り立ったところにあった市場をブラブラと散歩してみることにした。市場と言っても大きなものではなく、細い道の両脇にいくつかの商店がある程度だ。名前もわからない生の魚が無造作に並べられている商店、貝や小さな魚が入っているバケツが何個も並んでいる商店や、巨大なズッシリとした生肉の塊が並べられている商店もある。店と言っても、舗装もされてなく土埃が舞うような道にただ木を簡素に組み立てただけの台らしきものが置いてあり、その上に品物が並べているだけだ。店のおばさんは積極的に客を呼び込むでもなく、棒の先端にビニールの紐のがたくさんついたものをバサッバサと振り回してハエがたからないようにしている。立っていてもジワッと汗が出てくるほど暑いのに、魚や生の肉がむき出しでそのまま置いてあるのは若干信じがたかったが、意外と腐らないということなのだろうか。ペタンと潰れた豚の顔や、鼻だけ切り取ったものも売っている。豚の顔はどうやって食べるのだろう。
見たこともない太くて短いナス、トマト、ほうれん草や小松菜のような緑色の水々しい葉物野菜が山積みになっている店もある。市場ではキロ単位で販売をしており、人差し指を立てて1つ下さいなどと言ってしまうと1キロ渡されるハメになる。それでもわずか30ペソやそこらで買うことが出来るのだ。だいたいおばさんやおばあちゃんがやっているようだったが、彼女たちはこれらの大量の品物をどうやって仕入れてくるのだろう。その日販売する分を納品してくれる業者でもいるのだろうか。いろいろと疑問が残る。
その翌日、授業中にフィリピン人の先生が「週末は何してたの?楽しかった?」と聞いてきたものだから「行き先がわからないジプニーに乗って、市場があったから散歩してきたよ。」と言ったらすごく驚いていた。「1人で?それ、楽しいの?」となんだか真剣な顔をして聞かれた。
「うん。楽しかったよ。」と言うと「そんなことをする生徒はこれまで1人もいなかった。面白いことをするね。」と笑ってくれた。
またある週末には学校へ来たばかりの頃に一緒にバスケをしてすぐ仲良くなったフィリピン人の雑用係のドドンに誘われてローカル居酒屋へ行った事もあった。
「ジュン、少し歩くけどいい?」
「いいよ、行こう。」
学校の中で待ち合わせをして、ドドンと同僚の2人も一緒に行くことになった。学校の門とは反対方向に進んでいるため不思議に思っていたのだが、草が生い茂る庭のさらに奥の方にかくし扉のようなものがあった。裏口と言うにはあまりに裏すぎる場所にあり、生徒はこの扉の存在を知ることなく卒業していくのだろう。そこを出ると街灯もないような薄暗くて細長い道に出た。左右はバナナの木や背が高く葉っぱが大きい常夏の地にしか無い植物がたくさん生えていて、繁華街や街といった雰囲気は一切ない。
現地の友達がいなければまず近寄るようなところではない、と感じた。ましてや夜こんなに人気もなく建物も少ない道を歩くなんて、まずありえない。野良犬もウロウロとしている。しばらくすると二階建ての掘っ立て小屋のような建物が現れた。大型の台風でも来たらすぐに飛ばされてしまいそうな古さである。二階からは少しの明かりと音楽が漏れている。
「ここだよ。入ろう。」
ここだよ、と言われても見るからに民家である。心なしか傾いて見える。恐る恐る中に入ると小さなテーブルと椅子、それからバーカウンターらしきものが薄暗いライトに照らされている。音楽はカラオケの機械のようなものから流れていた。ドドンが暇そうにしている店員に何かを伝えると、フィリピンの定番ビールであるサンミゲルライトが6本入ったバケツを持ってきた。サンミゲルライトは日本のアサヒやキリンよりも薄くて水っぽく、とても飲みやすい。
「ジュン、なにか歌う?」
「え、歌は苦手だから僕は良いよ。」
「なんで苦手なの?」
「まあ…音痴だからね」
「気にすんなよ!歌って歌って」
そうは言っても日本の歌があるわけでもなく、お先にどうぞとすすめると少し嬉しそうにしてローカルソングを歌いだした。フィリピンに来て驚いたことの1つが歌である。陽気な人が多いからなのか、いろんな人がいろんな場所で歌っている。スーパーのレジ係の女性が歌いながらレジをしているのを見た時はなんだかすごく良いな、と思った。日本でそんな事をしたらクレームが来るだろうが、誰に迷惑をかけるわけでもないのだから本当はこのくらい自由でいいのだ。
楽しそうにしている彼らを見て、来てよかったなと思った。なぜなら間違いなく日本人1人で来れるような場所のではないからだ。当たり前のことだが、観光客は観光地の明るい場所にしかいない。何があるかもわからないくらい路地を入って看板もない小屋に1人で入ることなど不可能なのだ。
ビールをまた追加で頼み、2時間ほど飲んでほろ酔い気分のところで帰ることになった。ドドンの同僚が「すまないが実は…」と切り出す。お金がないという。一瞬高額な請求が来る詐欺かと思ってしまったが、お会計は500ペソだと言う。わずか1000円である。ビールを何本も飲んでそれなら詐欺どころか安いとさえ思った。なにより彼らは本当に申し訳無さそうな顔をしていたのだ。いいよ、払うよと500ペソを渡し、謝る彼らに気にしないでくれと伝えた。語学学校の雑用なら給料もそこまで高くはないだろうし、最初からそのつもりだったのだろうが、ガイドもしてくれて1000円程度ならむしろお得な気さえした。