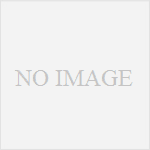第一章 生きてる実感③
思い返せばあの日がすべての始まりだったのかもしれない。あれは2010年の7月のこと。山梨の田舎から上京し、日本美容専門学校を卒業して、かねてより切望していた日本の流行の先端にある原宿・青山の美容室で働いていた。僕は2年目のアシスタントになっていて、日々忙しく過ごしていた。その夏僕は吉祥寺にあるグループ店舗に研修として1週間限定で勤務することが決まり、自宅がある下北沢駅の近くの東松原駅から吉祥寺に毎日通っていた。そんなある日の朝、その店舗の店長にこう言われた。
「えー、神奈川県にできる新店舗の人事異動の発表があります。各既存店舗から1人か2人ずつ移動になります。青山店からは…桑原が異動になります。」
なんとなく嫌な予感みたいなものがあったのを覚えている。正直素行があまりよろしくなかった事もあるし、なんだかわからないがそうなるような気がしていた。けど田舎から都会に憧れて上京してきたのに、神奈川の田舎に転勤になるなんてことは到底受け入れられなかった。そもそも青山店やその先輩たちが好きだったから離れたくなかった。
それを察したのか、スタイリストの先輩が「ちょっと裏で休んできなよ」と気を使って言ってくれ、お言葉に甘えて休んでいると店長が入ってきて、かすれた声で「これ本当は俺の役目じゃないんだわ。お前んとこの店長が言わなければならないことで…」と、ものすごく申し訳無さそうにしている姿を見て逆に申し訳なくなってしまった。
その日から自分の腹の中にあった情熱のようなものが消えた。転勤先で頑張ればいいだとか、美容師に場所は関係ないよとか、先輩たちはいろんなことを言ってきたが、正直何一つ響かなかった。そもそも僕は美容師になってからというもの、漠然とした疑問がずっと解消されなかった。理想と現実という言葉はよく聞くけれどまさにそんな感じで、目の前で日々起こることと、かつて思い描いていた未来に大きなギャップがあったからだ。それはもちろん自分自身の見積もりが甘いというだけだった。【ならば自分は将来的にどうしたいのか?】これがわからなかった。
異動の報せを機に、このままこの会社にいても自分はただのコマでしか無い、と思うようになった。とはいえ社会に飛び出たところでなにができるわけでもない無力な人間だ。何か大きなことはしたいけど何もできない、お金もない、人脈もない、経験もない。ただ美容師免許を持っているだけの奴といった滑稽さに泣きそうになったのを覚えている。様々な葛藤の中で毎日押し寄せてくる現実に、次第に疲れて生きる気持ちが落ちていくことも感じていた。転勤の話を聞いた瞬間、泣きながら店を飛び出して現実逃避を図ったという、エネルギッシュでアクティブな同期がとても羨ましく思えた。
そんなある日、シフトのミスで3連休が出来た。会社の規則的には3連休はダメらしいが、そんなことは知ったこっちゃないとその休みを使って東北に一人旅に行った。山形の山寺を巡り、そこで出会った大学生の女の子と意気投合して仙台駅東口の居酒屋で飲んだ。「夜行バスで今夜名古屋に帰るの」という彼女を見送ったあと、行く宛もなく仙台のクリスロードをふらついていると、ふいにギターの音色が聞こえてきた。ふと見るとひとりの青年がまさに今歌い始めるところだった。僕と同じように音に吸い寄せられて現れた酔っぱらいと今度は意気投合し、結局深夜まで路上で酒を飲み明かした。その後「おい、うち行くぞ!」と半ば強制的にタクシーに乗せられ、ギターの青年と僕は酔っぱらいの家に連れ込まれたのだ。
その夜出会ったのがギターを弾きながらチップを稼ぎ自転車で日本一周をしているタカシさんと、年金暮らしの酔っぱらいジョージさんという2人の男だった。ジョージさんの家でコタツにあたり、タカシさんと3人で飲み直す。散々飲んで一切頭が回らず、呂律も回ってなかったが、酔いにまかせて一通り自分の置かれた環境に対する愚痴をぶちまけてみた。すると黙って聞いていた2人が見事に口を合わせてこう言った。
「やめちゃえば?」
ジョージさんは続けてこう言った。
「踏ん切りがつかねぇだけだろ?いいか。この俺が作った牛すじの煮物を食って、そしたら明日糞が出るだろ。フンが。お前は宮城にフンギリをつけに来たんだ。だから食え!」
それを聞いたタカシさんが「そうだよそうだよ。クソして辞めちゃえ。」と笑っている。
「なんだよもう。俺はマジで悩んでるんですからね!」
そうは言いながらも、泣きたくなるのを我慢するくらいには嬉しかった。これまでは辞めることがいかに悪いかを説かれてきた。親にも先輩にも友達にも。相談した誰もが「辞めたらもったいないから」と僕に言ってきた。その度に僕は人の期待を背負って生きているような気がして、苦しくなった。一番辞めたら申し訳ないなとブレーキになっていたのは親の存在だった。専門学校にも行かせてくれ、これまでも散々迷惑をかけてきた。たった2年で仕事も辞めるような息子を人様に誇れるわけがない。そう思うと申し訳なかったのだ。
けど2人は「おう!そんなもんやめろやめろ!ガハハ」と無邪気に笑うのである。そして「旅にでろ!礼文島はいいぞ!」と言う。
「礼文島?どこっすかそれ。」
「え、知らないの?礼文島」
「知らないっすよ。どんなとこなんですか?」
かぶせ気味にジョージさんが口をはさむ。
「お前自転車で礼文島行ったのか!あそこは良いよなあ!」
「良いところですね!ホントまた行きたい!」
2人は僕をのけ者にしてあそこが良いだの綺麗だのしばらく話した後
「え、なんですか?なにがあるんですか?」と聞く僕に「礼文島のことは教えてあげないよ」と言った。そして自分で見てこい、と。僕は見たことも聞いたこともない礼文島という島に興味を持ったと同時に、日本のことを全然知らないんだなと気がついた。たくさん旅している2人がうらやましくて、すごくかっこよくて、輝いて見えた。1人は住所不定無職の放浪者、もう1人は住所はあるけど無職の飲んだくれである。こんな生き方もあるんだなと思った。
翌朝2人に別れを告げ、仙台駅前で直属で一番よく面倒を見てくれてた美容師の先輩に電話をした。
「俺、決めました。会社辞めます。今までいろいろやってもらったのに本当にすいません。」
「おう、そっか。まあ俺はいいと思うよ。また飲もうや。」
東京に戻り、辞表を提出し、2010年12月20日をもって退社することが決まった。それからはあんなに息苦しかった毎日に新鮮な空気が流れ込んできた。朝の電車が嫌じゃない。乗っていて涙も出ない。22歳にして僕は【病む】ということがどういうことなのか、またそれを治す手段を知った。環境を変えれば良い。それだけだった。
退職した翌日に、25名いた同期のみんなが吉祥寺駅の居酒屋で送別会を開いてくれた。そこに参加して朝5時まで飲んだあと、僕はそのまま始発に乗って西へと向かった。青春18きっぷと呼ばれるJR乗り放題切符を片手に。志半ばで美容師を辞めた僕がやりたかったことは、旅だった。仙台で出会ったタカシさんのように日本を旅していろんな景色を見たい。酔っぱらいのジョージさんのように「あそこは良かったなぁ」といつか言ってみたい。その一心で、とにかくバックパックを背負って東京を出たのだった。
鈍行列車を乗り継いで、昼過ぎにようやく目的地の滋賀県の近江高島駅についた。琵琶湖の西側にある湖西線の駅だ。駅前で300円のレンタル自転車を借りて、琵琶湖の湖畔にある白髭神社まで一気に駆け抜けた。初めて訪れた真冬の琵琶湖はそれはそれは寒かったが、僕の心はかつてないほど暖かく、エネルギーが溢れてくるのを感じた。
「おれは…‼自由だあぁぁ…‼」
車がビュンビュン通り過ぎる湖畔の道を全力で漕いだ。そして力のかぎり叫んでみた。大都会東京でそんなことを叫んでいたら不審者として通報されてしまうかもしれない。だが叫ばずにはいられなかった。だって、僕は自由なのだから。ここには僕を知る人は一人もいないし、今日は働かなくていい、明日も働かなくていい、西へ行くのも東へ行くのも自由だ!
白髭神社をあとにし、名古屋まで引き返した。叫んだはいいが、ふと冷静に考えたら今夜泊まる場所もないし冬の琵琶湖で寝る勇気はさすがになかった。とりあえず都会に行けばなんとかなるような気がして、最寄りの都会、つまり名古屋を目指すことにしたのだ。
実は僕にはその旅でやろうとしていたことが1つあった。それが【人と出会う旅】である。旅人のタカシさんのように、日本を巡りながら何か残ることをしたいという思いがあった。そしてそのためには僕からアクションを起こさなければならない。中高時代にバンドをやっていたしギターは弾ける、けど歌が下手。美容師の資格を活かして出会った人の髪を切るのもいいと思った。しかし僕は未だペーペーの見習いである。せめてスタイリストになっていれば髪を切る旅もできたであろう。悩んだ末に思いついたのが【握手の旅】であった。シンプルに出会った人と握手をする、ただそれだけだった。
名古屋の金山駅に着いた。初めて名古屋に来たが、さすが日本の三大都市のひとつで驚くほどに都会である。コンビニに立ち寄り〝名古屋〟と書かれたガイドブックを開くと〝大須観音〟というページがでかでかとあった。きっとそこはさぞ面白いところなのだろうと、大須観音があるという大須駅まで歩いてみることにした。大須駅には大きな商店街があり、その中心部には巨大な招き猫がいた。おもむろにそこに立ち、背負っていたバックパックを足元に降ろし、昨夜油性ペンでメッセージを書いた白いTシャツをバックパックに貼り付けた。
”日本列島握手の旅
僕と握手してください
東京から日本一周”
死ぬほど恥ずかしかった。始めるまで30分はモジモジしていた気がする。何をやっているんだろう?と自分でも思っていたが、とにかくアクションを起こすんだという意気込みがギリギリで羞恥心に打ち勝った。せわしない年末の夕暮れ時に突如現れた不審者に、人々はどんな反応をするのだろうという好奇心も手伝ってくれたからだと思う。しばらくすると1人の女性が声をかけてきた。
「あの…何してるんですか?」
「あ…えと…握手です。握手の旅。出会った人と握手してます。」
「え?テレビかなんかですか?」
「いや、違うんですけど、というか実は今始めたばっかりでして…」
「え?よくわからないけど握手したらいいの?」
「はい!お願いします!」
声をかけてくれたお姉さんは戸惑いつつも笑って握手をしてくれた。僕は嬉しさよりも意味不明なこの活動を受け入れてくれた人がいたことへの驚きの方がすごかった。イケるんだ…これ。そこからはおばあちゃん、家族連れ、ヤンキー、子供にいたるまであらゆる人が足を止めて握手をしてくれた。その数なんと100人。
まさかそんなに多くの人に受け入れてもらえるとも思わず、その結果にただただ驚愕した。その日は金山駅の端っこで寝袋にくるまって野宿をした。寒くて寒くて、とても寝れたものではなかったが、なんだか心は充実しているような感覚があった。東京のアパートで寝るよりも温かさを感じるこの冷たい地面。今日僕が社会的に言えばいわゆる”馬鹿なこと”をした結果出会えた多くの人々の手から貰った温もりもまだ感じられた。
「生きるってなんだろう?」
口に出したわけではない。けど金山駅の暗闇の中、心の中で僕は僕に問いかけた。やりたいことをやるために入った会社、結局嫌で辞めたけどそこでの日々はただただ辛いだけのものではなかった。お客様、先輩、いろんな人に出会えて、いろんな人に世界を広げてもらった。教えてもらった。成長されてもらった。ありがたいことなのだが、何かが違った。
思えば、その日までは会社や店や美容師という職そのものが自分の人生の大部分だった。どこで働いているだとか、どういう肩書だとか、そんなことばかりを気にしていた。僕はそれらがずれ始めたときに病んでしまった。自分でコントロールできないものに自分をゆだねて生きていれば、どうしようもない時も、苦しい時だって産まれてしまう。【僕がありきの美容師や肩書でいいじゃないか】と思った。僕は僕だし、他人は他人。握手をしたいと思ったのだから、したらいい。今日はうまくいった。もうすこしこのまま頑張ってみよう、と思いながら浅い眠りについた。